B.LEAGUEレフェリーのプライドと挑戦


プレーヤー・ファーストの精神
片寄達さん(55歳)、
レフェリー歴32年、教員

バスケは小学校5年生の頃からやっています。ですので、バスケに関わって44年くらいになりますね。これほど長くバスケと関わるとは思ってもみませんでした(笑)。今は高校教員をしながら、B.LEAGUEのレフェリーをしています。
レフェリーとして大切にしていることは、プレーヤー・ファーストの姿勢です。試合をスムーズに進行させることはもちろん、プレーヤーがパフォーマンスを最大限発揮できる環境をつくることが、結果として試合に関わる皆さんの満足にもつながると考えています。
レフェリーとして難しさを感じるのは、プレーヤーの意図や感情を把握しながらジャッジをしなければならない場面です。試合の流れやプレーヤーの心理を読み取り、公平かつ的確に判断することは、常に大きな課題となります。また、最も重要なのは、ルールの理解と正しい適用、そして円滑なコミュニケーションだと考えています。プレーヤーやチーム全体のパフォーマンスを最大限引き出せるように、レフェリーとしての役割を果たし、試合をより良いものにすることを常に心掛けています。

そして体力の維持も重要な要素の一つですね。ランニングや軽い筋力トレーニングを中心に、怪我の予防のためのストレッチも行っています。試合を通じて最高のパフォーマンスを発揮するために、日々のトレーニングは欠かせません。

長年レフェリーを続けていく中で、日本のバスケットボールは大きく変わりました。特にこの10年間の変化は著しく、B.LEAGUEの発足後は観客動員数が飛躍的に増え、各種メディアでの露出も増えました。学校でも「先生、昨日の試合でテレビに映ってたね!」と言われることもあります(笑)。バスケットボールが、より多くの人に親しまれるスポーツになったことを実感しています。

試合を通じて私が伝えたいのは、プレーヤーやスタッフ、そして観客が互いにリスペクトし合うことの大切さです。全ての関係者が一丸となり、日本のバスケットボールを盛り上げていく、私もその一端を担いたいと考えています。以前は、選手・コーチ・マネージャー・トレーナーくらいしか関わることができませんでした。しかし、今のB.LEAGUEには、さまざまな関わり方があります。バスケットボールが好きな方は、ぜひ積極的に関わり、一緒にバスケットボールシーンを盛り上げてほしいですね。
公平なジャッジと信頼関係
前花直哉さん(54歳)、
レフェリー歴30年、教員

普段、私は高校で保健体育を教えています。中学校、高校、大学とずっとバスケをしてきました。
私がレフェリーとして大切にしていることは、公平な判断と対応です。同じゲームはありませんので、予想していないことが起きる場合があります。どちらのチームにも不利にならないよう、公平に対応します。長くレフェリーを続け、経験を積んでいると、ジャッジした際に選手が「こう思うだろうな」「こう言ってくるだろうな」とある程度予測できるようになります。その予測があることで、余裕を持って選手と接することができ、より適切な対応をすることができます。
私たちレフェリーにゲームを任せてもらうためには、チームや選手との信頼関係が大切です。信頼関係を築くためにも、コミュニケーションは欠かせないと考えています。また、体力の維持も重要な仕事の一つです。年齢とともに関節が硬くなるため、しっかり動かさなければなりません。そのため、ストレッチは欠かさず行っています。また、ほぼ毎日3kmのランニングを続け、コンディションを整えています。

長年レフェリーを続けてきて、日本のバスケットボール界は大きく変わったように感じていますね。特に身長の高い選手がアウトサイドでも積極的にプレーするようになり、技術の向上により見応えのあるゲームが増えました。選手が素晴らしいプレーをし、試合がスムーズに流れ、観客が一体化する…。そんな瞬間に立ち会えると、レフェリーでありながらも「いいなあ」と実感します。

試合を通じて私が伝えたいメッセージは、選手にはそのゲームにフィットした判定を示し、試合に集中してもらうこと。観客には、選手が集中することで生まれるアグレッシブでワクワクするゲームを楽しんでもらいたいと考えています。
これからレフェリーを目指す若い世代には、挑戦する気持ちを持ち続けてほしいと思います。2026-27シーズンからB.革新(「強化」「経営」「社会性」の3つの軸に沿って、2026年からリーグ構造の変更を伴う、大きな変革)により、さらにレベルの高いゲームが繰り広げられ、レフェリーの重要性も増すでしょう。そこに挑戦していけることを幸せに感じながら、頑張ってほしいですね。

謙虚さと感謝を胸に
芳賀聡さん(54歳)、
レフェリー歴30年、地方公務員

私がレフェリーとして大切にしていることは、謙虚さと感謝の気持ちです。レフェリーでいることには、家族や職場の理解が必要です。自分だけの力でコートに立っているのではないからこそ、常に感謝の気持ちを持って取り組まなければならないと感じています。難しいと感じる瞬間は、いつでも、どんなゲームでも訪れます。簡単なゲームは一つとしてありません。その難しさこそが、私が今もレフェリーを続けている理由の一つかもしれませんね。レフェリーとして最も重要だと思うスキルは、ゲームマネジメントです。勝敗に関わる立場だからこそ、負けたチームも納得して結果を受け入れられるよう、公平で的確な判断を下すことが求められます。

体力の維持も重要な課題です。私は、普段は公務員として働いています。審判がある時は金曜日に移動して、日曜日に自宅へ戻るという生活を送っています。土日はゆっくりしたいと思うこともありますが、コート上には緊張感と興奮を味わえる特別な空間が広がっています。おそらく、平日の私とレフェリーとしての私では顔つきが違うのではないかと思います(笑)。シーズン前には週3日程度の走り込みを行い、体力をキープしています。シーズン中は調整程度に週1回、約5kmのジョギングを行っています。また、入浴前には毎日腕立て伏せや腹筋をして体形を維持しています。

かつては競技人口の多さのわりにマイナーな印象がありましたよね。ここまで注目を浴びる競技になるとは、想像もしていませんでした。バスケットボールの魅力は面白さだけでなく、その限りない可能性です。レフェリーを含め、多くの人がそれぞれの立場から試合に関わることで、よりレベルの高い試合が生まれ、観客の皆さんにも一層楽しんでもらえると思います。

これからレフェリーを目指す若い世代には、ルールを正しく適用するだけでなく、バスケットボールの可能性を引き出すことの重要性を伝えたいです。レフェリーは辛いこともあります。しかし、誰かのために頑張ることが、自分の成長につながる瞬間が必ず訪れます。目先の結果にとらわれず、レフェリーという役割を通じてバスケットボールを存分に楽しんでください。

長年レフェリーとして活躍してきた彼らは、それぞれの視点からバスケットボールを支えてきました。公平なジャッジ、選手への敬意、そして謙虚な姿勢。こうした姿勢が、バスケットボールの発展を支えてきたのです。B.LEAGUEの試合を観る際には、ぜひレフェリーの存在にも注目してみてください。

『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI』において、エニタイムフィットネスの特設ブースを試合会場である「LaLa arena TOKYO-BAY」内に設けました。ランニングマシンやトレーニングマシンを設置し、会場を訪れた皆さまにトレーニングを体験していただきました。






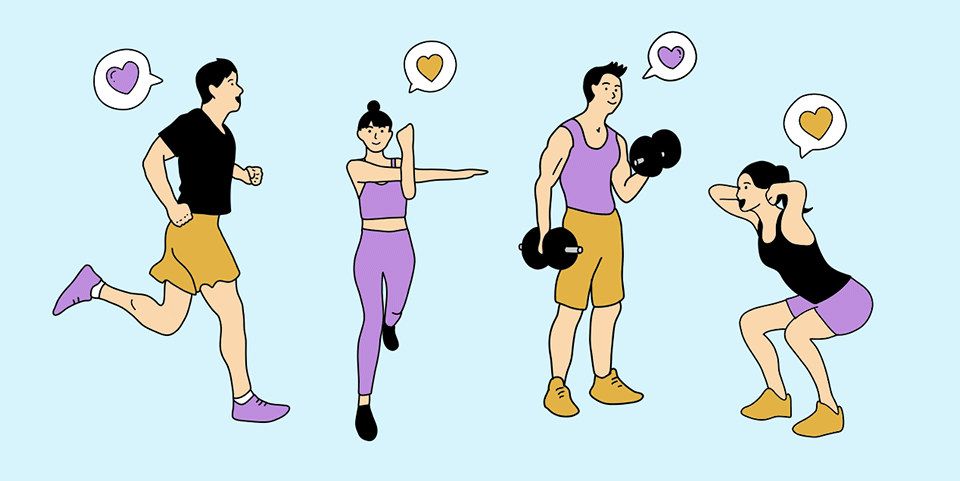

試合が白熱する中で、公正なジャッジを下し、試合をスムーズに進行させるレフェリーたち。彼らはまさに縁の下の力持ちであり、バスケットボールの試合になくてはならない存在です。教員などの本業と両立しながらコートに立ち続けてきた彼らは、まさに二足のわらじを履くプロフェッショナル。今季または来季で、B.LEAGUE担当審判の定年を迎えるベテランレフェリーの皆さんに、これまでの経験や大切にしてきたこと、そして未来へのメッセージを伺いました。長年にわたり活躍してきた彼らの言葉には、バスケットボールへの深い愛情と誇りが込められています。