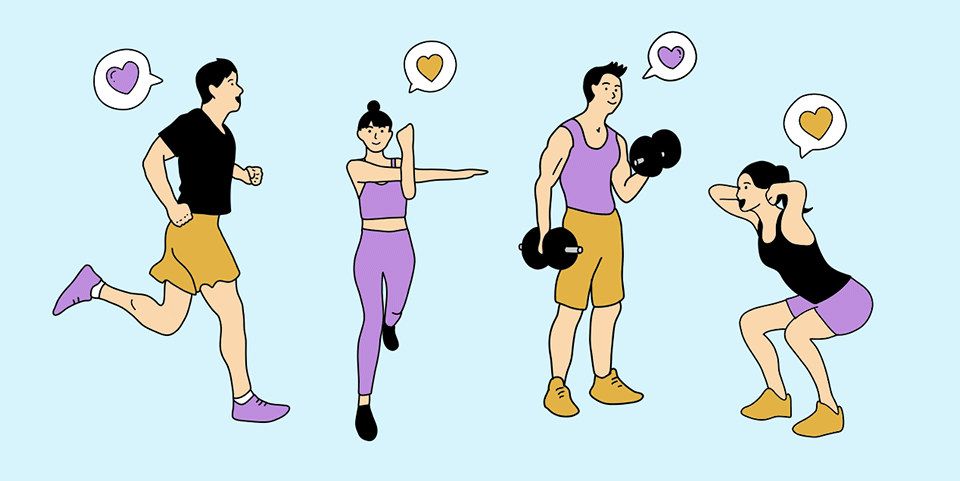最新脳研究が明らかにした
「やる気」を出す方法とは?

やる気がどうしても出ない時は
「ジムで一番重いものは何か? それはジムの扉だ」という筋肉格言がある。おそらくアメリカンジョークの類いなのだろうが、トレーニーの気持ちをよく表している。「今日こそはジムに行こう!」と思っていても、「雨が降っているなぁ」とか「ご飯食べたところだし」「シューズが運動向きじゃないな…」なんて言い訳をして、ジムを素通りしたことがある人は多いだろう。かく言う私も何度、素通りしたことか。
だけど、不思議なものでその「重い扉」を開けると、気持ちが変わる。多くの人たちがそれぞれの運動をしている。さらにマシントレーニングをしていくうちに体が温まってきて、運動や休憩を繰り返していると心地よい気持ちになってくる。これは脳内麻薬ともいわれているエンドルフィンや、やる気と快感のスイッチであるドーパミン、心を安定させるセロトニンが出ている、脳の快感フルコース状態。トレーニーハイとでも言うのだろうか。しかし、この辺りまではどの筋トレ本にも書いてある話だ。実はこのやる気、自由自在に操る方法があるという。

「私という現象」、高校生と脳を語り尽くす』
池谷裕二(著)
講談社 2,420円(税込)
脳研究者の池谷裕二さんの『夢を叶えるために脳はある』(講談社)は高校生に向けて行った特別講義を再構成したもの。最新の脳にまつわる研究が分かりやすく説明されている。670ページ以上もある大著だが、高校生との会話形式で進むので読みやすい。しかし、高校生と侮るなかれ。生徒たちの理解度が高く、知識も豊富。ぼんやりしていると置いていかれるので集中力が必要だ。
講義は夢を見ている脳の話を導入とし、心とは何かというテーマに移る(この導入部分を読むだけでも、本著を手にする意味はあるはず)。脳の潜在能力、時間という概念、記憶、生きるとはどういうことか、人工知能へと話が流れていく。脳という医学的な切り口ではあるけれど、人間とは何かという哲学的な分野にまで話が及ぶ。脳は「すべての人にあるもの」だし、「日々付き合っているもの」なので、書かれていることすべてを自分事のように思える。読めば読むほど、人間を、いや自分自身を理解することにつながる気がする。
さあ、話を戻そう。「やる気」をどのように操るか。
池谷さんは陸軍士官学校の「志望動機」に関する論文を例に出している。「あなたはなぜ、士官学校を希望したのですか?」 その答えの多くは「国に貢献したい」「愛する家族を守りたい」「出世したい」という、動機を達成するための「手段動機」だった。一方で「陸軍そのものが楽しそう」と答えた人たちがいた。これは心の内側から発せられる「内発的動機」だ。つまり、前者は陸軍士官学校でなくても医者でも弁護士でもいい。士官学校はこの二つのパターンの動機を追跡調査した。すると、内発的動機だった人たちの方が出世をしたという。「楽しむ力」「ご機嫌に生きる力」が大きい方が物事はうまくいくと、この論文は説いている。
この「楽しむ力」は報酬系という快感の専用回路から生まれる。中でも「側坐核(そくざかく)」という脳部位を活性化させればモチベーションが高まる。つまり、やる気が出る。側坐核を活性化する実験の被験者に「どうやって活性化させたのか」を調査したところ、多くの人が「楽しい事を考えた」という。これはスピリチュアルな話でも精神論でもなく、科学的な観点から「楽しい事を考えるとやる気が出る」ことは証明されている。
具体的には「楽しかった事」を明瞭に一分以上思い出すと良いそうだ。嘘だと思うなら、ちょっとやってみてほしい(ちなみに私は大きな魚を釣った記憶を思い出したら、本当にやる気が出た)。ただ、「あの頃は良かったなあ」というような漠然とした思い出は「それに比べて今は」とかネガティブな感情が湧き上がるので良くないそう。ポイントは「明瞭に思い出す」こと。一生付き合う脳だからこそうまくハックして、やる気UP対策をしてみてはいかがだろう。また、本著によって脳の仕組みを知ることは、やる気UPだけでなく、今後の人生でも大きな武器になりそうだ。