日本バスケットボール協会(JBA)公認
プロフェッショナルレフェリー
FIBAレフェリー加藤誉樹さん

バスケを支えるプロフェッショナリズム

Profile
加藤 誉樹(カトウ タカキ)
日本バスケットボール協会(JBA)公認のプロフェッショナルレフェリー。B.LEAGUEでは「最優秀審判賞」を8年連続で受賞。FIBA国際審判員としてFIBA バスケットボールワールドカップ 2023では3位決定戦を担当するなど、国境を越えた信頼を獲得している。

プレーヤーから審判になって
見えてきたもの
加藤さんは、選手から審判になったと伺っています。
大学時代、膝の怪我に悩んでいて、思うようにプレーができずにいました。チームと相談する中で、大学バスケの運営に携わるようになり「審判への道もある」とすでに審判を始めていた先輩たちから言われました。悩みましたね。家族が大変応援してくれていましたし、そのおかげでバスケが強い高校、大学に進学することができました。なので、当時はなかなか受け入れられず、まだやれるんじゃないか、膝も治るんじゃないか、そんな葛藤がありました。
ある日、大学に向かうバスの中で、ふと考え方が変わったんです。選手ならいつかは引退の時が来ます。だけど、審判としてバスケに関わることで、引退後も多くの人脈ができ、プレーヤーでは得ることができない経験が積めるのではないかと。バスを降りてすぐに父に電話をして、プレーヤーを引退し、審判への道に進むという決意を伝えました。今となっては、その選択のおかげで今の自分がいると思っています。それに、偉大なNBAプレーヤーと共に一枚の写真に収まるような経験もできました。

プレーヤーと審判では見えてくる世界が違いますか?
審判を始めてすぐに「審判はバスケの中にある別の競技だ」と感じました。それまで福岡大学附属大濠高等学校、慶應義塾大学といった高いレベルの学校でバスケを経験してきたので、私はバスケを知っているつもりでした。しかし、審判は全く違うのです。駆け出しの頃は見えないプレーがたくさんありました。それでも経験を重ね、コツをつかんでいくことで、選手の動きが見えるようになったり、タイミングの取り方を学んだりします。そこにはプレーヤーとして技術を習得する過程と似たような部分がありました。
審判の世界。それは奥が深く、幅の広い世界でした。審判の面白さに出会い「まだまだバスケには習得できる領域がいっぱいあるぞ」とわくわくしましたね。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUE審判を続ける中で成長を実感したタイミングはありましたか?
「この地点から成長した」という瞬間はありません。審判を始めた当初から思っていたのは、プレーヤーとしてバスケに打ち込んだ熱量と同じくらい審判に打ち込むということでした。そうすれば、プレーヤーとして活躍するよりも審判で活躍できる可能性があるのではないかと考えたのです。
急に成長するというよりは、階段を少しずつ上っていく感じですね。試合で何ができて、何ができなかったかを振り返り、次の試合で修正する。新しい課題が出てきてそれにアプローチするという感じです。ただ、面白いのは、この「階段」は、らせん状になっていて、同じようなカテゴリーの悩みでもレベルの上がった悩みに次々とぶつかっていくのです。この壁をクリアしていくことを20歳の頃から今日までやっています。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUEコートの中と外の経験も
つながっている
2017年にプロフェッショナルレフェリーになったことは、一つのターニングポイントではありませんか?
そうですね。プロになったので他の人よりも熱意を持たなければいけないという思いはありましたが、それまでもプロ意識を持って審判をしていました。つまり、私の中での審判はずっと地続きなんです。コートの中と外の経験も地続きだと思っています。プロの審判をする前は金融機関にいたのですが、外でのいろんな経験がコート中に生きることもありますし、コートでの経験、精神的なタフさがコートの外に生きることもあると思います。私はすべてが地続きだと思います。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUE試合中の様子を教えてください。エキサイトすることもありますか?
感情的になることはほとんどないですね。感情的になることがいい結果に結びつかないことを知っているからでしょう。例えばジェスチャー一つでも、感情的にシグナルを出すと、場の状況を把握できていないような印象を与えてしまいます。”さも当然”かのようにシグナルを示すことで、選手には全部が分かっていてこの判定につながっているのだと表現できます。
ただ、試合中に感情が無いわけではなく、「うまくできなかったこと」や「さっきの判定は違う見方もあったかも…」という反省の感情はあります。冷静にゲームを見ながらも、もう一人の自分が自分を見ているような感じですね。
FIBA(国際バスケットボール連盟)では、マインドフルネスも取り入れており、呼吸法などを学んで実践しています。練習でできることが試合でできないってことがありますよね。これを最終的に突き詰めていくと、プレーヤーも審判も最後の壁はメンタルなんです。私は「Here(ここ)」と「Now(今)」という二つの言葉を大切にしています。何か過去の出来事や判定が頭をよぎったら、「ここ」と「今」に集中するよう自分に言い聞かせています。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUEさまざまなスポーツでカメラシステムを使った「ロボット審判」や人工知能が判定を行う「AI審判」などが取り入れられています。審判が「人間」であることの意味は何だと思いますか?
私は「人間の審判」には意味があると思います。あるテニスの大会で機械審判を導入したところ、選手がラケットを破壊する頻度が増えたそうです。これが本当だとすると、バスケでもラフプレーが増える可能性があります。人間はミスを起こします。ですが、人間だからこそコミュニケーションで解決できることもありますよね。単に判定が正しければ良いというわけではなく、人と人の関係性が重要なんですね。
私は日頃から、選手とコミュニケーションを取ることを心がけています。今の課題は、ネイティブの外国籍プレーヤーが違和感を持たない形でコミュニケーションを取れる英語スキルを身に付けることです。例えば、『FIBA バスケットボールワールドカップ 2023』の3位決定戦(アメリカ対カナダ)で私は笛を吹きました。勝てば銅メダルを持ち帰ることができます。選手たちは生活も、この後のキャリアもかかっているでしょう。彼らは精神的にギリギリの状態なわけですから、審判が言葉でまごまごしていたり、違和感があってはいけません。「違和感を覚えさせないこと」も、ゲームをより安全でスムーズに終わらせる上で重要でした。語学力を含めたコミュニケーション能力が求められますね。
審判もアスリート同様に
体を鍛える理由

加藤さんの、日々のトレーニングはどのようなものですか?
有酸素トレーニングと筋力トレーニングをしています。有酸素は大体1日30分ぐらいで、時期によって内容を変えています。国際審判のライセンス更新時にはシャトルラン(往復持久走)のテストがあるので、それに向けた特別なトレーニングをすることもあります。
基本はランニングで、膝の状態によって時にはバイクに切り替えることもあります。試合翌日は軽いジョギング、週の中盤は5〜6kmを走るなど強度を変えています。遠征時も必ず現地のエニタイムフィットネスを探してトレーニングしているんですよ。ホテルにチェックインをして30分ほど休憩したら、エニタイムに向かいます。全国の主要な街のエニタイムの場所は頭に入っていますね。あそこのアリーナだったら、ホテルはあそこだから、あのエニタイムだなって(笑)。

筋トレは部位ごとに分けていて、胸の日、肩の日、背中の日というようなローテーションで毎日行っています。胸の日は1時間ほどかけますが、他の日は30分ほどですね。体づくりも審判として重要な仕事だと思うので、毎日コツコツやっています。審判もアスリートとしてしっかり体を鍛えている姿が見えた時、ジャッジにも説得力が出てきます。体力づくりはもちろんですが、ゲームをスムーズに進める上で大事な要素としてトレーニングに取り組んでいます。

メンタル面では音楽を聴くことが多いですね。『FIBA バスケットボールワールドカップ 2023』3位決定戦の前日、ホテルに一人でいたのですが、「自分で大丈夫かな?」と、緊張で震えが止まらなくなったんです。準備はできているはずだったのに、びっくりしましたね。そこで「失敗を恐れない邦楽」とGoogleで検索して、YOASOBIの『群青』に出会いました。歌詞を見ながら聴いたら感情が込み上げました。「何回でも、ほら何回でも、積み上げてきたことが武器になる」「今でも自信なんかない、それでも」「大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ」という気持ちになれました。最近はMrs. GREEN APPLEなども聴いています。やっぱり、音楽には大きな力があるんだと思いますね。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUE33%ずつの責任を担って
コートに立つ
審判をしていて良かったと思う瞬間はどんな時ですか?
両チームのプレーヤーが全力を出し切り、お客さんも盛り上がる中で、選手やチームがしっかりゲームの結果を決め、ロッカールームに帰れた時は格別です。緊張の糸が切れる瞬間です。ただ、そういう時ばかりではなく、むしろ「もっとこうできたら良かった」と振り返ることも多いです。
本当に審判が必要とされるのは、グレーゾーンの判定です。明らかなファウル、明らかに問題がないプレーは本来選手同士で解決できます。つまり、私たち審判が必要なのは「当事者だけでは解決できない真ん中の部分」です。そのため、どんな判定をしても不満を持つ人が出るのは当然で、常に判定を振り返り改善する必要があります。

トップリーグの試合では3人の審判がコートに立ちます。時には新人の審判と組む場合もあるのですが、私たちは同じ権限なのです。試合前のミーティングでは「今日の主審は私ですが、3人で33%ずつの責任を担いましょう」と話しています。誰か一人が飛び抜けた経験を持っていても、3人がそれぞれの役割をしっかり果たさなければゲームはうまくいきません。ちなみに残りの1%については、「今日はたまたま主審が私なので、ジャンプボールを上げる役目として1%いただきます」などとお話ししています(笑)。
これから『2028年 ロサンゼルスオリンピック』や『FIBA バスケットボールワールドカップ 2027』で主審をしたいという目標はありますが、これらはまだ時期的に遠いものです。今は目の前の1試合、1クォーター、1プレーを大切にして取り組むことを積み重ねています。そして、先ほど申し上げた大きな目標から逆算して、審判のスキル、英語力、トレーニングなど必要な準備を着実に進めています。
 写真提供:(C)B.LEAGUE
写真提供:(C)B.LEAGUE加藤さんはインタビューなどで、他の審判やTO(テーブル・オフィシャルズ:審判とともに、ゲームの公正かつ円滑な管理を担う役割)への感謝を口にすることが多いですね。ご自身だけでなく全員でゲームをつくっているという感覚が伝わってきます。
私一人の力でうまくいくゲームは一試合もありません。審判は3人のクルーで担当し、次の試合にバトンをつないでいくのです。最優秀審判賞をいただくのも、個人的にはとても恐縮に感じています。
TOも審判と同じぐらいか、時にはそれ以上のプレッシャーを感じています。自分の押すボタン、判断一つでゲームが違う方向に行ってしまうかもしれないというプレッシャーの中で仕事をしています。また、コートの汗を拭くモッパーも、皆さんすごいこだわりを持って仕事をしています。選手や審判だけでなく、それぞれの立場で全員がプロフェッショナルとして関わることで、ゲームが素晴らしいものになっています。私たち審判はまだ目に見える位置にいますが、日の当たらない場所で働いている方々にも光が当たってほしいと思っていますね。バスケのゲームには本当に大勢が関わっています。ぜひ、バスケのゲームを見る時に、選手以外の存在も見てもらえたらと思います。






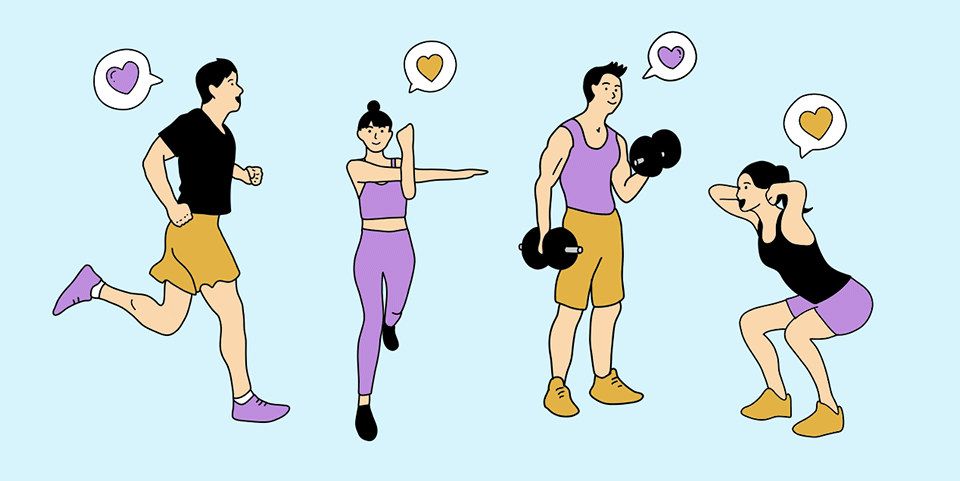

コート上の一瞬が選手の運命を変える。試合を見極める目を持つ人がいる。怒号と歓声が交錯する熱狂の中、冷静沈着にホイッスルを吹く加藤誉樹さんだ。高身長の選手に囲まれても、その存在感は決して埋もれない。日本バスケットボール協会(JBA)公認のプロフェッショナルレフェリーとして、B.LEAGUEで8年連続「最優秀審判賞」を受賞した彼の実力は揺るぎない。さらに国際舞台でも評価され、FIBA バスケットボールワールドカップ 2023では3位決定戦の重責を担うなど、その信頼は国境を越えて広がっている。プレッシャーと向き合い続ける審判の神経は鋼のように鍛えられていた。今回は、そんな加藤さんにお話を伺いました。